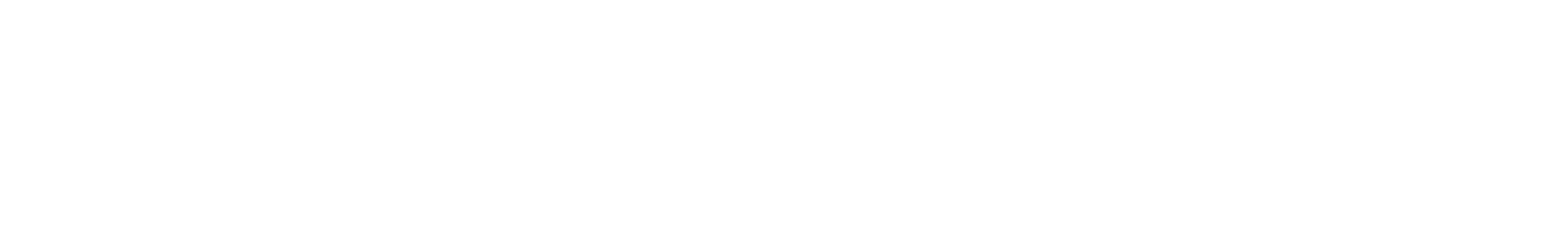メタ認知を身に着けよう
皆様、こんにちは。
東京都あきる野市にあります生活介護笑スリーの佐藤です。
今回は障害者支援をする上で欠かせないメタ認知についてお話をしていきたいと思います。
自己決定
昨今の福祉サービスではご利用者様の「自己決定」に重きを置くようにいわれています。
福祉サービス事業所側がその方にとってどんな支援が望ましいのか一方的に提案するのではなく、ご利用者様が人生において何を優先し何を必要と考えるのかを重視してサービスを提供していく形が主流となっています。
しかし、知的に障害があるご利用者様を対象とする事業所、取り分け知的重度の方の場合はご利用者様の自己決定が困難なケースがあります。
そういった場合には狭い範囲であっても自己決定ができるようになる支援をしていくことから始まります。
例えば
- 話し言葉でコミュニケーションが取れない方であれば、代わりにイラストカードや写真カード等を用いて意思が主張できる方法を提案してみる
- 選択肢が多いと選ぶことが難しい方には、ある程度選択肢を絞った上でどれが良いか選択していただく
等の支援をすることがあります。
また、自己決定ができない状態にある場合には、自己決定ができる状態になっていただくことを目指していきます。
障害特性によるストレスや不安感が強い場合には合った環境をご用意する、環境に慣れる支援をする等から始めていきます。
しかし、福祉サービス事業所に長く勤めていると、そういったご利用者様の自己決定を意識しつつも、ついつい支援者側が先回りしてその方に合った支援を考えてしまうことがよくあります。
上手くいった前例があるとそれに倣い、似たケースに対しては同じような手法を用いることで上手くいくこともありますが、これが過ぎるとご利用者様の自己決定というよりも支援者側の思い込みによる主観的な支援になってしまいます。
メタ認知
やはり似たケースであってもそれぞれのご利用者様で何を優先し、何を好むのかの違いはありますので個別に考えていく必要があります。
こういった考え方を維持するためにはできるだけ「客観的視点」「客観性」を養う必要があります。
こういった物事の捉え方を養うのに「メタ認知」を高めることが役に立ちます。
メタ認知とは、自分の思考や行動を客観視することです。メタは、ギリシャ語の「meta」から派生した言葉で「高次の」「より上位の」という意味があります。
見る・聞く・話す・読む・考えるといった認知活動を、もう一人の自分が俯瞰して捉えることをメタ認知と呼ぶのです。
認知活動を俯瞰して捉える意味で、発達心理学者 ジョン・H・フラベルは、メタ認知を「認知についての認知」と定義しています。
ざっくりというとメタ認知はこのような意味合いがありますが、細かく知りたい方はWEBに情報が転がっていますので調べてみてください。
メタ認知を養うことで主観を取り除いて俯瞰的に自分を捉えられ、主観と客観を分けて考えることが可能になります。
ではメタ認知を養うためにはどのようにすればいいでしょうか。
トレーニング方法として「セルフモニタリング」「マインドフルネス」等が挙げられます。
セルフモニタリング
セルフモニタリングは、自分の行動や思考、感情を観察し、評価・修正するトレーニング方法です。日々の業務で「どこがうまくいったか」「課題は何だったか」「改善点は何か」といった問いを自分に投げかけ、振り返る時間を設けることで、自己理解が深まります。この習慣化により、自分の強みや課題を客観的に把握し、行動を調整する力が養われます。
セルフモニタリングは、メタ認知能力を高め、より効果的な仕事の進め方をサポートするシンプルかつ実践的な方法です。
マインドフルネス
マインドフルネスは、今この瞬間の自分の感情や思考、体の状態に注意を向けるトレーニングです。瞑想や深呼吸などを通じて、自分の内面に意識を向け、評価や判断をせずに観察することがポイントです。
これにより、自分の感情や思考の動きを俯瞰的に捉える力が養われ、衝動的な判断や行動を抑え、冷静な対応が可能になります。
こういった方法の他に個人的に役立ったトレーニング方法をご紹介します。
レッツメタ活
それは未知の知識を得て、できれば体験をすることです。
これまで知らなかったことを知る、体験をすることで物事を捉える時に多角的な視点を持つことができます。
人と話したり、本を読んだり、研修に参加してみたりと色々な方法がありますが、そうはいっても仕事をしながら新しいことを体験しに行くのはなかなか大変です。
私自身、スーパーインドア派なので週末は好き好んで外に行くことはあまりありませんし、未知の分野に飛び込んでいくようなエネルギッシュさもあまりない人間です。
そのため、本や音声コンテンツ(podcast)から情報を得て強く興味を持てたものは実際に体験してみよう、より調べてみようといった風にして様々な知識や経験を楽しく蓄えられるように勤しんでいます。
怠惰な私は楽しめなければ続かない人間なので、いかに好奇心を持てて楽しめるかを重要視しています。
音声コンテンツ(podcast)であれば朝の身支度中、通勤中、家事等のお供として気軽に聞くことができるのも利点になります。
そこで、個人的にメタ認知向上に役立つ音声コンテンツ(podcast)をご紹介いたします。
いくつもご紹介したいところですが、今回は厳選した3つのコンテンツをご紹介していきます。
歴史を面白く学ぶコテンラジオ(COTEN RADIO) /COTEN inc.
spotify/apple podcast
歴史上の偉人や出来事を時代背景を含めて紹介してくれる音声コンテンツです。
「フランス革命」「吉田松陰」「ゴッホ」「マケドニアのアレクサンドロス大王」等など、テーマは多岐にわたります。
コテンラジオは情報の正確性を担保するために時間をかけてリサーチを行い、知識がない人でも楽しく歴史が学べるコンテンツとなっています。
この音声コンテンツを聞いていると、時代によって常識や文化は変化するものであり、自分が常識だと思っていることが常ではないと認識することができます。
また、後世に名を残す偉業を成した偉人であっても、捉える角度によってはただの困った人であるように思えたり、見方によっていくらでも人や物事の認識が変化することを学ぶことができます。
豊富なリサーチがもたらす臨場感ある解説はとても興味深く、歴史好きにはもちろん歴史に興味がなかった人でも楽しく聞くことができるのでおすすめの音声コンテンツです。
ミモリラジオ-自然の面白さを聴く / MIROI
spotify/apple podcast
ミモリラジオは自然界から一つのテーマをピックアップし、その面白さを笑いと共に読み解くトーク番組です。
普段何気なく目にしている木々や草、自然現象、生き物たちの知られざる生態について学ぶことができます。
「クジラ」「キノコ」「オオカミ」「カミナリ」等をテーマにして深掘り、わかりやすく解説がされています。
誰かが設計したわけでもないのにあたかも狙って作られたかのような自然界の仕組み、生態系は聞けば驚くこと間違いなしです。
自然界の知識を得ると今までは気にも留めなかった日常風景を違ったピントで見ることができ、新鮮な気分を味合うことができます。
こういった体験から物事の見方に新たな角度が加わる・・・ような気がしています。
また、大いなる大自然の話を聞くことで自分という人間の小ささを感じることができるので、ちょっとした悩みがしょうもないことに思えます。
a scope /NEWS PICKS
spotify/apple podcast
a scopeは第一線で活躍する研究者を招待し、リベラルアーツについて語っていきながら、私たちが生きる「この世界」を捉え直していくトーク番組です。
こちらの番組ではあらゆる業界の研究者や専門家等から話が聞くことができ、経済学~宗教まで幅広いテーマが取り上げられてますので、自分が所属する業界以外の重厚な知識を得ることができます。
取り分け福祉業界は一般企業とは毛色が異なる点が多く知識が偏りやすいのですが、幅広い業界の知識を得ることで物事の着眼点を増やすことができます。
自分の世界では常識だと思っていることが、他の世界では全く正反対であるなんてことを認知する機会を得ることができます。
以上3つのトーク番組をご紹介させていただきました。
どの番組も無料でpodcast,spotify等で聴くことができるので是非聴いてみてください。
無知の知から始まる
かの有名な哲学家ソクラテスの考えで「自分に知識がないことを知る」=「無知の知」というものがあります。
- 自分は知識がないことを自覚することは恥ずかしいことではない、むしろ知識がないことを自覚するからこそ新しい知識を得ようとする
- 知っているという先入観が真実とのギャップを生んでしまうことがある
こんな考え方です。
言われてみれば当然に思える考えですが、無意識に「これは知っている」と思ったり、知らないことが恥ずかしくて知っているふりをしてしまうことは誰でもあるのではないでしょうか。
偉人の言葉を引用するとそれっぽく見えるので使ってみましたが、そこまでソクラテスのことを勉強しているわけではないので、これもまたある種の無知の知を自覚していない状態でしょうか。
メタ認知を高めて自分が知っていること、知らないこと、わからないことを整理した上で物事を思考していけると支援の質も向上していくと思っています。
皆様もメタ認知力を高めるためにメタ活やっていきましょう。